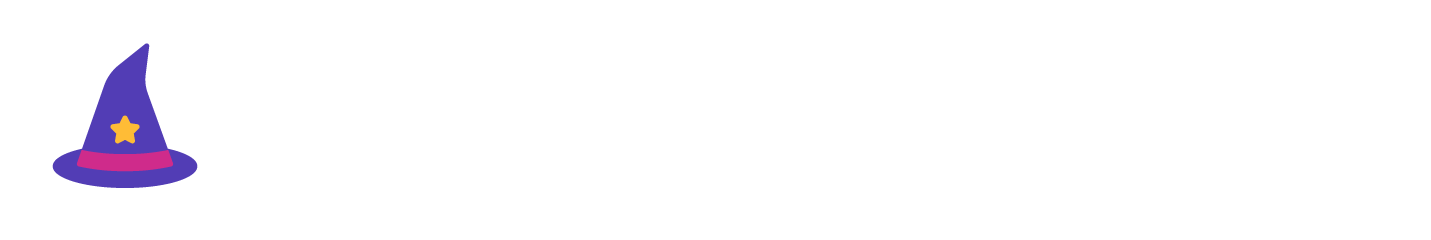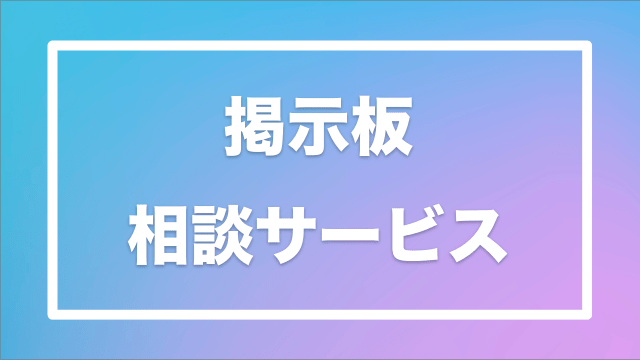ユングのタイプ論に基づいた性格診断テストでは、あなた自身の性格タイプを知り、自分自身や周りの人々を理解することにつながります。MBTIや16TEST、16Personalitiesなど様々な性格診断がありますので、まずは試してみませんか?

診断テストはこちらから無料で診断できます(約5~10分)
前回は、ソシオ二クスの8つの心理機能を用いた精神構造である、モデルAについてお話ししました。

このモデルAの8つの心理機能が当てはまるようなそれぞれ、第一機能〜第八機能にはそれぞれ、自我・超自我・イド・超イドといった区間により分類されます。
今回はそういった分類について、自我ブロック・超自我ブロック・イドブロック・超イドブロックおよび、それら4つのブロックのうち、意識/無意識の話を中心にしていきたいと思います。
もくじ
モデルAの2つのブロック
まずモデルAには意識ブロックと無意識ブロックがあることを説明します。
意識ブロックとは、ソシオ二クスの自我ブロックと超自我ブロックを含んでいるような区間となります。同様に無意識ブロックとはソシオ二クスのイドブロックと超イドブロックを含んでいるような区間となります。
まずは意識ブロックについて説明します。
意識ブロックとは?
意識ブロックとは、自分を包み込んでいる外の世界と自分との関わりをあなたが意識しているような区間となります。この意識ブロックを通して、人は自分を包み込んでいる外の世界を認識しています。
意識ブロックに該当している心理機能は、日常生活でも使っていて理解できるブロックであり、得意苦手はありますが、実生活で意識しているブロックとなります。
意識ブロックには、第一機能と第二機能を含んだ自我ブロック、第三機能と第四機能を含んだ超自我ブロックが含まれています。
無意識ブロックとは?
無意識ブロックとは、自分の内部に関するあなたの考え方や自分の世界への関わり方のように、無意識に意識している区間となります。この無意識ブロックは、意識ブロックを通して理解したような情報を自分の中に取り入れることで、無意識のうちに情報処理され使用されています。
無意識ブロックに該当する機能は、一般的には日常生活上でも知覚することができず、意識的にコントロールすることはできない心理機能となります。困難に遭遇した際などに、無意識のうちに使っているような心理機能であるといえます。
無意識ブロックには、第五機能と第六機能を含んだ超イドブロック、第七機能と第八機能を含んだイドブロックが含まれています。
意識ブロックと無意識ブロックの分離について
ソシオニクスでは、意識ブロックは自分が自分の外の世界に対してどういう風に認識するのか、無意識ブロックは自分が自分の内側の世界に対してどういう風に認識するのか、といった分類を行なっていますが、これはAという命題に対して・B(テーゼ)とC(アンチテーゼ)という対立した意見があるとしましょう。しかし、BとCを解決するようなD(ジンテーゼ)という真理があるとします。
全ての人は、そのようにDという真理を持ちながら、自分の内側と外側で異なる意見を持ちバランスを保っているという仮説のもと作成されている心理テストであると考察します。
例えば、憲法や法律のような完全なルールがあるとします。そのルールをルールとしてみる人もいますが、ルールを悪用したように、ルールに対し「これはルールじゃないよね」といった風に物事を違う角度からみる人もいるでしょう。
意識ブロックでは、あなたがどちらの立場を取っているか?という意味合いを示しており、無意識ブロックでは、意識ブロックと対極的な立場を持っていることを意味しています。
厳密には哲学的なお話になるので、ここでは省略しますが、要するにソシオ二クスのブロックは哲学的なバランスに基づいて作成されていることが1つの解釈としてあります。
ソシオニクスの自我とは?
ソシオニクスの自我(自我ブロック)とは、その人にとって最も使っていて心地が良くしっくりくる心理機能であることが言えます。他の人と会話をする時、チームワークをする時など、最も自然な形で現れる心理機能です。
自我に現れる心理機能は、超自我やイドといった対極的な心理機能によって対立することに頭を悩ませることが多く、それらは、どちらも正しくまた矛盾を抱えています。
自我に該当する心理機能を使った場合、素早く情報を知覚し処理することができます。また、最も得意な分野であることから、自分自身、自信を持っていることも多いです。
一方で、自信を持っているからこそ、自我ブロックの心理機能を使いすぎて、世界の全てがその人の自我ブロックに該当する心理機能であるという錯覚を起こしやすいと言えます。
また、自我ブロックに該当する心理機能は、得意なだけではなく、本人の哲学的立場に一貫していることから、使っていても心地よく、ついつい長時間使いがちと言えるでしょう
他者から見ても同様に、自我ブロックはその人の特徴的になると言えるでしょう。
適職やチームの中での適正を考えた時に、最も注目するべきなのは自我ブロックといえます。自我ブロックに該当するような心理機能はその人の「生きること」の理由そのものであることとも言えます。そのため、矛盾なく行動に一貫するため、自我ブロックを生かすことができれば、輝くことができるでしょう。
また、人間関係の相性等については、「クアドラ」という概念を使用しますが、またの機会に紹介することにします。
- 自信のある心理機能である
- 異なる心理機能を使う他人よりも、自分をあてにするような心理機能である
- このブロックで知覚判断した世界が全てと考えがち
- 罪悪感やストレスを感じることは少ない
- 意欲的に使用し、磨こうとしている
ソシオニクスの超自我とは?
ソシオ二クスの超自我(超自我ブロック)とは、その人が意識的に使用することは多いものの、自我ブロックと対立しているような心理機能であることから自我ブロックから制約を受けながら使うことになります。
自我ブロックはその人のアイデンティティとなるような心理機能を含んでいますが、超自我ブロックの心理機能は自我ブロックを実現するために、使わざるおえないと考えているような心理機能を含んでいます。
すなわち、超自我ブロックに関して本人はあまり関心を持たないような心理機能で、困難に直面した環境下では、あまり機能を発揮することができなくなるような弱い機能とも言えるでしょう。
超自我ブロック下にある心理機能はその人が社会に適合するために必要な心理機能であるという風な考え方をすることもあります。つまり、その人本人が強く意識している自我ブロックの心理機能に対して、超自我ブロックはそのバランスを取るような社会の要求するその人の心理機能であると言えるでしょう。
一般的には社会に適合する訓練期間とも言えるような、学生期間(12~18歳)の間に身につけていくような心理機能と言われていますが、自我ブロックと矛盾する心理機能ですので、コントロールするのは苦手な機能とも言えます。
- 社会規律を守る為に身に着ける
- 自我ブロックのバランスを取っている
- 間接的に自我を助けている機能
- ストレスを感じると使えなくなったり、失敗を恐れるようになる
ソシオ二クスのイドとは?
ソシオ二クスのイド(イドブロック)とは、その機能を使おうと思えば使うことはできるものの、あまり重要ではないと考えているような心理機能であります。自分の特徴を更に伸ばそうという取り組みや、退屈なルーティンのような作業に使うことはあっても、集中して使うような心理機能ではないと言えます。
イドブロックに該当している心理機能は、人は使いこなすことができると言われています。ただ、イドブロックを使用するのは意識的に使用するというわけではなく、困難の状況下で使用することになることがあるブロックでありますが、本人は気づいておらず、また興味すらないです。
イドブロックを使う為には、自我ブロックを抑制する必要がありますが、本人はそれほど価値を感じ取ることもないので、イドブロックが機能するのは、危険回避することや生存本能を担保する場合に限ります。
以上の立場から、長時間使用することも難しい心理機能であります。
イドブロックは、自我ブロックのように、主張の激しいブロックではありますが、使うと自身の意識的な立場と違うのでストレスを感じます。
- 意識すると使用することはできる
- 長時間使用することができない
- 自身の自我と対照的なので、使うとストレスを感じる
- 危険回避に無意識に使う
ソシオ二クスの超イドとは?
ソシオ二クスの超イド(超イドブロック)とは、できる限り避けて通りたいと思っているような心理機能になります。超イドに該当している心理機能を使わなければならないシーンでは、人に任せたり、雑に扱うことが多く、多くの場合、本人の苦手な心理機能となっています。
超イドは双対関係にあるような、お互いを補完しあえる関係の時には相手にさらけ出すことができます。その為、自身の超イドを自我として持っている人とは比較的仲良くなりやすい傾向があります。
超イドブロックは、その人の未熟さを強く表しているブロックであり、MBTIでは第三機能・劣勢機能に該当するように、コントロールすることが苦手ですので、人生において超イドブロックのアドバイスや助けを求めることが多いでしょう。そして、何より、超イドブロックはおざなりに扱われる為に、無視されてしまいます。
超イドブロックを使用するシーンは、その人が自我ブロックを使い何か実現したいと考えた時や、人生に物足りなさを感じた時に使用すると言われています。
- 他人に頼りたい心理機能
- 適当に扱っている機能
- 他人の目を通すことで、初めて認識できる心理機能
- 状況が悪化した際に初めて意識するようになる
①MBTIへのいざない - ユングの「タイプ論」の日常への応用
16タイプ性格診断 - MBTIを知りたいあなたは絶対に読むべき1冊。入門書としても応用本としてもトップクラスに評価されている本で、お値段こそすこし高いですが基本的な考え方を体系的に説明してくれている1冊になります。1冊目を探しているあなたにも、ざっくり理解しているあなたも必読です。
②ユング心理学でわかる8つの性格
心理機能を知りたいあなたへお届けする1冊になります。16性格診断を勉強しているとFeやNiといったアルファベットが出てきますが、そのようなアルファベット(心理機能)を理解することで16性格診断を理解することができます。この本も入門書としてはとても優秀で、オススメの一冊です。
③新版エニアグラム【基礎編】
9タイプ性格診断 - エニアグラムを知りたいあなたは絶対に読むべき1冊。エニアグラムの本は数多くありますが、筆者はこの本が最も理解しやすく感じました。9タイプの特性をまずは理解したいあなたに、エニアグラムをもっと理解したいあなたにオススメの一冊になります。