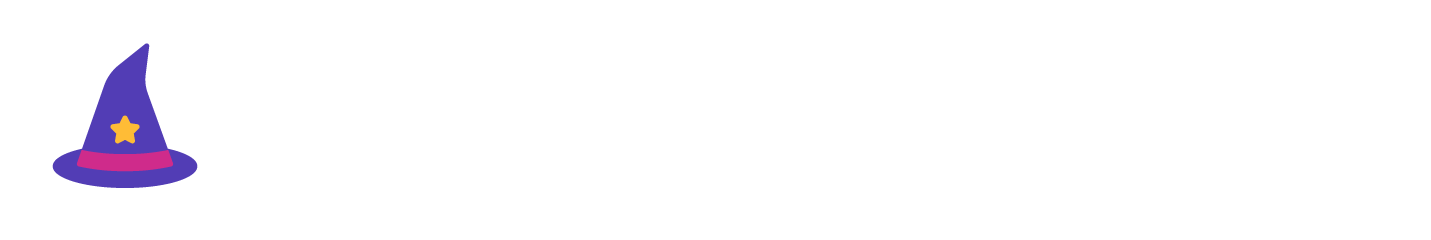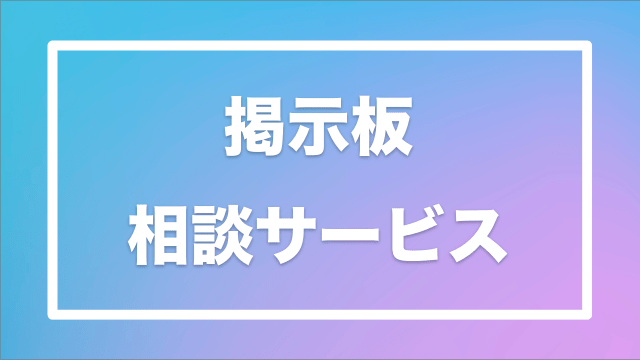ユングのタイプ論に基づいた性格診断テストでは、あなた自身の性格タイプを知り、自分自身や周りの人々を理解することにつながります。MBTIや16TEST、16Personalitiesなど様々な性格診断がありますので、まずは試してみませんか?

診断テストはこちらから無料で診断できます(約5~10分)
16種類に性格を分類することで自己・他者理解を深めるツールとしてMBTIを当ブログでも良く取り上げていますが、性格同士の相性については実はMBTIでは分からないとMBTIの公式協会でも言われています。
では、どのように相性が決められているのか、という疑問ですが、結論から言うと、「ソシオニクス」というMBTIを発展させた理論に基づいて、相性が決められています。MBTIについて知らない方は以下の記事を見てみてくださいね。

もくじ
ソシオニクスについて
日本では血液型で性格診断することがありますが、アメリカ人やロシア人は自身の血液型を知らないことすら多いと言われています。血液型の性格診断は正直根拠が曖昧ですよね。
アメリカ人やロシア人は代わりに、複数の心理問題から性格を分類することで性格診断するMBTIやソシオニクスといった性格診断をしていることが主流です。
つまり、日本人の血液型占いが、アメリカ人にとってのMBTIであり、ロシア人にとってのソシオニクスということです。
つまり、MBTIがアメリカの主流な性格診断テストであることに対し、ソシオニクスはロシアの主流な性格診断テストです。
ソシオニクスの発明を行ったのは、1970年〜1980年代に活躍した、リトアニアの心理学者Aušra Augustinavičiūtė氏によるもので、独自のモデルを用いることで人間の心理構造を説明します。
ソシオニクスは、ユングのタイプ論と、ポーランドの精神科医のAntoni Kępińsk氏による情報代謝の2つの理論を組み合わせて作られた理論です。
MBTIもユングのタイプ論に基づいて作成されているので、この点は共通しています。

ソシオニクスで使う8つの心理機能について
MBTIと同様に、ソシオニクスでも8つの心理機能を使います。
こちらはユングのタイプ論の記事にて、詳しく説明したので、簡易的に説明します。
人間の心の働きは、外向きに働く動き(外向性)と内向きに働くような動き(内向性)があることをユングは知覚機能および判断機能にまで発展させました。
知覚機能とは、情報をどのように受け取るかといった機能で、五感を通して実際にあるものを感じる(S型)のか、あるものの中に眠っている見えない潜在的なものを感じ取るか(N型)です。N型は直観型で、S型は感覚型です。
これらの感覚機能にも内向性・外向性があるとユングは発見し、内向的直観・外交的直観、内向的感覚・外向的感覚と言う風に分類しました。
ここでは、感覚型について説明しますが、
内向的感覚とは、規律正しさや、経験的なことを意味しています。一方で外向的感覚とは、外からの刺激を意味しています。具体的な行動や体験に対する耐性を意味しています。
知覚機能と同様に、人間の判断にも、人の感情を重要視するか(F型)、物事の本質や真理を重要視するか(T型)といったように分類し、内向性・外向性をもたせました。F型は感情型で、T型は思考型と言います。
ソシオニクスはMBTIとは少し解釈が異なることがあるので簡単に触れておくと、
ソシオニクスは知覚/判断という分け方ではなく、その心理機能の合理性について分類しています。
N/Sの分類については、人間が選ぶことなく、情報を受け取るような非合理的な要素として分類し、T/Fの分類については、人間が選んで情報を整理するように合理的な要素として分類しています。
ソシオニクスとMBTIの違いとは?
ではソシオニクスとMBTIが異なる点はどこにあるのでしょうか?
タイプの表記方法が異なる
ソシオニクスには、SLEタイプとか、ILEタイプなど、MBTIのESTPタイプやENTPタイプと表記が異なります。
MBTIではF型を感情型と言いましたが、ソシオニクスではE型(Ethical, 倫理型)となります。またMBTIのT型(Thinking, 思考型)はソシオニクスのL型(Logical, 論理型)であり、MBTIのN型(iNtuition, 直観型)はソシオニクスのI型(Intuitive)となります。
その他は同じですが、表記の方法が異なり、MBTIは外向/内向,直観/感覚,思考/感情,柔軟/判断という順番で表示しますが、ソシオニクスではそのタイプの第一機能+第二機能+外向/内向(MBTIでいうE/I)という表記をします。
つまり、ENTP型ですと、第一機能は外向的直観(Ne)であり、第二機能は内向的思考(Ti)ですので、ILEタイプとなります。
ソシオニクスは8つの心理機能全てに触れている
MBTIでは1つのタイプにつき、第一機能から劣勢機能まで4つの心理機能を割り当てていましたが、ソシオニクスでは、第一機能から第八機能まで存在します。
MBTIでは残りの4つの心理機能については、触れていないのですが、ソシオニクスでは、そちらまで言及していると言う形になります。
ソシオニクスでは、潜在意識と顕在意識という分類を行い、8つの心理機能をそれぞれ当てはめています。このような構造をモデルAと言い、ソシオニクスについての話になるとよく取り上げられます。
タイプ同士の相性を知ることができる
組織のチーム編成を考えるときにはそれぞれの相性を考える必要がありますよね。MBTIでは、相性がわかりませんが、ソシオニクスでは理解することができます。
これらは、それぞれのタイプがみている世界を哲学的な立場からどう考えているか、どのような判断を取っているかといったような分類を行ったり、それぞれの心理機能の使い方の関係性から理解することができます。
つまり、実際にMBTIを使って、組織編成やチームの編成を考えたいと言う人にはソシオニクスをオススメします。
①MBTIへのいざない - ユングの「タイプ論」の日常への応用
16タイプ性格診断 - MBTIを知りたいあなたは絶対に読むべき1冊。入門書としても応用本としてもトップクラスに評価されている本で、お値段こそすこし高いですが基本的な考え方を体系的に説明してくれている1冊になります。1冊目を探しているあなたにも、ざっくり理解しているあなたも必読です。
②ユング心理学でわかる8つの性格
心理機能を知りたいあなたへお届けする1冊になります。16性格診断を勉強しているとFeやNiといったアルファベットが出てきますが、そのようなアルファベット(心理機能)を理解することで16性格診断を理解することができます。この本も入門書としてはとても優秀で、オススメの一冊です。
③新版エニアグラム【基礎編】
9タイプ性格診断 - エニアグラムを知りたいあなたは絶対に読むべき1冊。エニアグラムの本は数多くありますが、筆者はこの本が最も理解しやすく感じました。9タイプの特性をまずは理解したいあなたに、エニアグラムをもっと理解したいあなたにオススメの一冊になります。