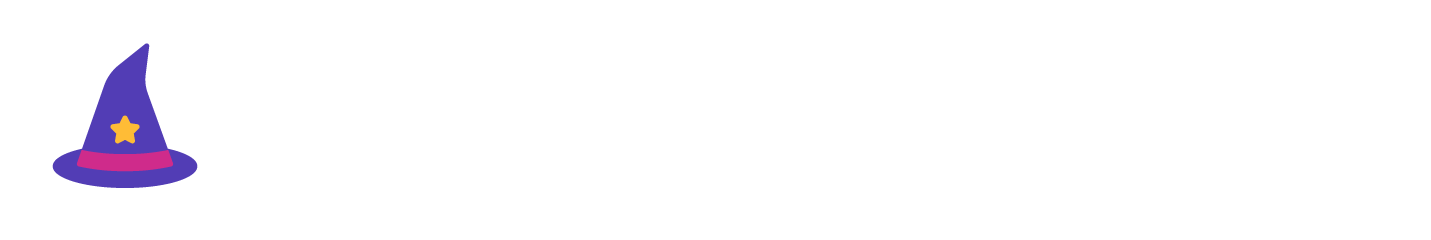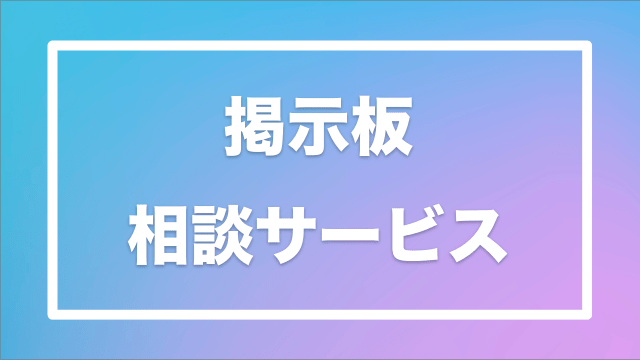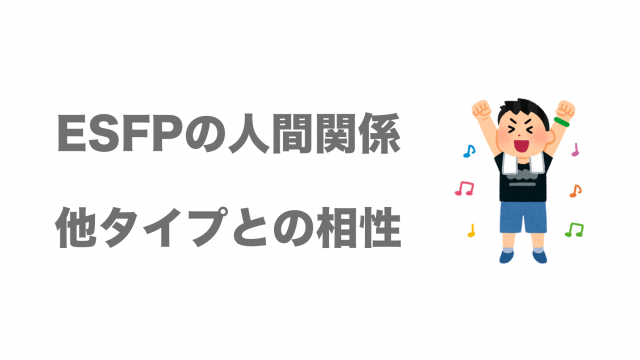ユングのタイプ論に基づいた性格診断テストでは、あなた自身の性格タイプを知り、自分自身や周りの人々を理解することにつながります。MBTIや16TEST、16Personalitiesなど様々な性格診断がありますので、まずは試してみませんか?

診断テストはこちらから無料で診断できます(約5~10分)
MBTI(Myers Briggs Type Indicator)とは、アメリカの心理学者のマイヤーズ氏とブリックス氏により開発された性格診断のことですが、この性格診断はカールユング氏の代表著作の「タイプ論」の中で定義された心理機能を組み合わせることで、人間を16タイプに分類するような性格診断になります。

タイプ論や、心理機能についての記事は以下のリンクより参考にしてみてください

今回、なぜMBTIの診断結果が変わるのか?という記事を書いているかという背景ですが、MBTIを学ぶ上で根本的な思想、本質となってくるのはカールユング氏の思想であり仮説です。性格診断を学ぶ上で、生かしていく上では、そういった思想や仮説に反する理論、つまり間違った認識が多く広まっている可能性があることから記事にすることにしました。
もくじ
カールユング氏の思想
集合的無意識はアーキタイプからなっている。(Carl Jung 1875~1961)
上記はカールユング氏が残した代表的な名言のうちの一つになります。このユング氏の思想や仮説が発展させられていることから、MBTIやソシオニクス、ネオユングまで幅広く影響範囲があることは想像するのも容易ですよね。
カールユング氏の思想は上記の流れからアーキタイプや心理機能を生み出していると考えられています。
(1) 世界中のどの場所でも、どんな文化でも、神話やシンボルなどは、時代を超えて、何故ひどく類似しているのか、その類似性に気が付いた
(2)これらの類似性は、ある種として生まれた私たちが現在も共有している経験や知識から生まれた産物であろう
(3)上記のように世界に共有された経験は「記憶」という形で以下の2種類の形により保持されている
(3-1) 人間の行動パターンをまとめ、「アーキタイプ*」という形で保持されている
(3-2)”集合的無意識*”という、全人類に共通して存在する形で保持されている
(4) したがって、私たちは誰もが「世界を理解するために」これらのアーキタイプを使用する集合的無意識を持って生まれてくる。
(*アーキタイプとは、遺伝子のように先祖から引き継がれる記憶・象徴の一部のことです。アーキタイプは、全人類に共通して存在するものと考えています。)
(*集合的無意識とは、私たちの個人的経験には一切基づいていない意識のことである。例えば、「母性」や「父性」というテーマを生み出すために根底にあるもので、集合的無意識により、何かしらテーマを生み出すことができるということになります)
MBTIのタイプは変わるのか?
結論からすれば、MBTIは根本的に変わらないことを定義として持っているので、本来は変わるはずがないです。
これは、類型論vs特性論の内容にもなりますが、MBTIは類型論であり、その性格や心理機能に対して優劣をつけるのではなく、どちらに寄った心理機能を使っているかで解析します。わかりやすく説明すると、MBTIでは基本的にその人が「左利きか右利きか」のように生まれ持ってきた資質に基づいて、性格を分類しています。
これらは上記に説明した、ユングの思想および前提条件に一致するもので、ユングは人間は生まれ持って性格となるような資質(アーキタイプ/集合的無意識)を持って生まれてくることを前提としています。
何故MBTIの診断結果は変わってしまうのか?
あなたが、診断をしたサイト・コンテンツはどのような科学的根拠に基づいたサイトだったでしょうか? 自身のタイプを知るために補助してくれるコンテンツやサイトは多く存在しているものの、上記の前提条件である「根本的に変わらない」診断結果を出してくれるサイトは恐らく少ないでしょう。それは、内部の実装やロジックが曖昧であり、ユングの仮説やMBTI自体の概念を完全に投影できてないから、と言えるでしょう。
MBTIの事実として、50%の確率で性格が変わる
MBTIは実は、数十年以上、専門的な心理学者の中で批判を受け続けています。何故、批判を受け続けているのかという理由が、今回のテーマにもなっている「MBTIの診断結果が変わってしまうこと」です。
ある調査によると、5週間すると50%の確率で、違うパーソナリティとして診断されてしまったという結果を得られてしまい、前提条件とズレを起こしてしまっているのです。
http://fortune.com/2013/05/15/have-we-all-been-duped-by-the-myers-briggs-test/
最後に
カールユング氏の前提条件、およびMBTIの前提条件は人間が生まれ持っての性質であり普遍なものを指していましたが、実際のテストでは普遍ではない結果が得られるために、その信憑性が得られないという話になりました。
つまり、MBTIのテストの中では、本当の自身のタイプを理解することはできないので、信頼性の高いテストを受講する、あるいは他の性格テストを併用することで自己理解・他者理解に生かすというのが現状の解決法でしょう。(当サイトでもより性格なMBTIテストを作成することを検討しています)
①MBTIへのいざない - ユングの「タイプ論」の日常への応用
16タイプ性格診断 - MBTIを知りたいあなたは絶対に読むべき1冊。入門書としても応用本としてもトップクラスに評価されている本で、お値段こそすこし高いですが基本的な考え方を体系的に説明してくれている1冊になります。1冊目を探しているあなたにも、ざっくり理解しているあなたも必読です。
②ユング心理学でわかる8つの性格
心理機能を知りたいあなたへお届けする1冊になります。16性格診断を勉強しているとFeやNiといったアルファベットが出てきますが、そのようなアルファベット(心理機能)を理解することで16性格診断を理解することができます。この本も入門書としてはとても優秀で、オススメの一冊です。
③新版エニアグラム【基礎編】
9タイプ性格診断 - エニアグラムを知りたいあなたは絶対に読むべき1冊。エニアグラムの本は数多くありますが、筆者はこの本が最も理解しやすく感じました。9タイプの特性をまずは理解したいあなたに、エニアグラムをもっと理解したいあなたにオススメの一冊になります。